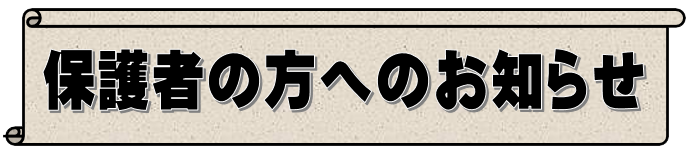文字
背景
行間
日誌
学年・学級だより
避難訓練 【全校】
火事の時の避難訓練です。
第二次避難所の公園へ学校から避難する訓練をしました。


0
委員会紹介集会 【全校】
後期の委員会が始まりました。
委員会の委員長が、委員会の仕事やメンバーの紹介をしました。

0
台風18号への対応について
今夜から明朝にかけて関東地方に台風18号が最接近するとの予報が出ていますが、現時点では、東京への直接的な影響は少ないと考えられます。
明日6日(木)は通常授業の予定です。台風通過後のため、通学等には十分気を付けて登校してください。また、風雨等により危険を感じる場合には、ご家庭の判断で、登校を遅らせても構いません。遅らせる場合は引率をお願いします。
明日6日(木)は通常授業の予定です。台風通過後のため、通学等には十分気を付けて登校してください。また、風雨等により危険を感じる場合には、ご家庭の判断で、登校を遅らせても構いません。遅らせる場合は引率をお願いします。
0
和食器体験【6年生】
クラスごとに和食器体験をしました。
教室で、日本の古来の文様や日本の食文化についてのお話を聞いたあと、
ランチルームで実際に和食器を使って給食を食べました。



0
9月のひまわり
雨ごとに秋の気配を感じるこの季節、ひまわりでは子どもたちが元気いっぱいに様々な活動に取り組んでいます。9月のひまわりの活動をここで少しご紹介します。
【ワークタイム: 「先生ツイスター」 】
色がついたサイコロを振ります。出た色とその色に置く手足を先生に「○色に(右手or左手or右足or左足)を置いてください。」と言って伝えます。手足の左右は自分で選ぶことができます。あえて先生たちが辛そうな置き方を指示する児童や安心できるような置き方を指示する児童など様々でした。この活動を通して、楽しめただけではなく左・右の確認ができました。
【運動: 「呼吸法」 】
腹式呼吸の練習をしました。吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにへこませます。この動きが意外と難しく、うまくいかない児童もいました。お腹に手を当てたりボールを置いたり、うつぶせになってみたりすることで、少しずつお腹に空気を入れる感覚が分かってきたようでした。腹式呼吸ができると姿勢がよくなるそうです。
【ひまわりタイム: 「よく聞くかるた」 】
2人組で行いました。1人が読み札に書かれている形の3つの情報(大きさ、色、形)を暗記し、ペアを組んだ相手に伝えます。そして、もう一人が伝えられたものを表している絵カードを取りに行きます。ただ覚えて取りに行くだけではなく、取りに行くまでの間に数を数えさせたり、計算させたりと様々な妨害刺激を入れて負荷を与えました。子どもたちの記憶にとどめるための方法は様々で、自分に合った方法をそれぞれ確認することができました。

0
明日は東光寺小まつり
明日は雨の予報ということで、東光寺小まつりは
雨バージョンで行います。
体育館と校舎1階を使っておこないます。、
ご来校の際には、上履きをお持ちください。
雨バージョンで行います。
体育館と校舎1階を使っておこないます。、
ご来校の際には、上履きをお持ちください。
0
ミニ文化祭 宣伝集会
9/30 はミニ文化祭です。
3年生から6年生までがクラスごとにお店を出します。
今日の集会では、そのお店の宣伝をしました。




全クラス載せられなくて、ごめんなさい。
3年生から6年生までがクラスごとにお店を出します。
今日の集会では、そのお店の宣伝をしました。




全クラス載せられなくて、ごめんなさい。
0
ものづくり特別授業【5年生】
日野自動車の方に来ていただいて、ものづくりの特別授業がありました。



日野自動車の自動車づくりの仕方やダカールラリーのお話を聞いた後、
プレス機で、金属板をプレスしたり、
ねじを回してみたり、
トラックの装備を触ってみたりしました。



日野自動車の自動車づくりの仕方やダカールラリーのお話を聞いた後、
プレス機で、金属板をプレスしたり、
ねじを回してみたり、
トラックの装備を触ってみたりしました。
0
三連休の過ごし方について
明日から三連休になります。また、その後飛び石連休が続きます。学校でも指導いたしましたが、ご家庭でも以下のことについてご注意ください。
〇交通事故に気を付ける。自転車は交差点で止まり、ヘルメットをかぶる。
〇誘拐に気を付ける。知らない人について行かない。出かける時は、誰とどこへいつ帰るを伝える。
〇お祭りなどで、夜遅くまでいない。夜は、お家の人と一緒に出掛ける。
〇ハチの活動が活発になっています。本日市内の小学校で校外学習中、10人がハチに刺され、救急搬送されることがありました。ハチがいる場所には近づかないようにしましょう。ハチは、髪の毛や黒っぽい服に向ってくることがあるそうです。
また、台風16号が日本列島に向って来ています。連休明けの週に関東地方に影響が出てくるかもしれません。先日配布しました印刷物が台風対応の基本となります。
〇交通事故に気を付ける。自転車は交差点で止まり、ヘルメットをかぶる。
〇誘拐に気を付ける。知らない人について行かない。出かける時は、誰とどこへいつ帰るを伝える。
〇お祭りなどで、夜遅くまでいない。夜は、お家の人と一緒に出掛ける。
〇ハチの活動が活発になっています。本日市内の小学校で校外学習中、10人がハチに刺され、救急搬送されることがありました。ハチがいる場所には近づかないようにしましょう。ハチは、髪の毛や黒っぽい服に向ってくることがあるそうです。
また、台風16号が日本列島に向って来ています。連休明けの週に関東地方に影響が出てくるかもしれません。先日配布しました印刷物が台風対応の基本となります。
0
着衣泳 【6年生】
今年の水泳指導は、今日でおしまいです。
最後に、6年生が着衣泳をしました。


服が体にまとわりつく感じに驚いていました。
最後に、6年生が着衣泳をしました。


服が体にまとわりつく感じに驚いていました。
0
本日の給食
日野市GIGAスクール構想
リンクリスト
Netモラル(保護者向け)
カウンタ
2
3
0
8
4
0
9
過去認定状況
学校情報化優良校

(2016年4月から2018年3月まで)

(2016年4月から2018年3月まで)