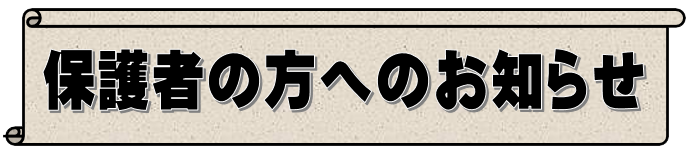文字
背景
行間
日誌
学年・学級だより
えさやり
牛の舌はザラザラしているので、なめられると少し痛いかもしれませんとのこと。チモシーの端を持って、えさをあげます。なめられて、思わず、ぎゃーとの声も!
牛に喜んでもらえるように、えさをあげられるかな?

牛に喜んでもらえるように、えさをあげられるかな?

0
乳しぼり
滝沢牧場のホルスタインのあさひちゃんの乳しぼりをしています。
乳しぼりをして、温かいー。柔らかいー。との感想。しぼらせてもらった後は、ありがとうとあさひちゃんに伝えます。優しい気持ちになります。

乳しぼりをして、温かいー。柔らかいー。との感想。しぼらせてもらった後は、ありがとうとあさひちゃんに伝えます。優しい気持ちになります。

0
滝沢牧場
滝沢牧場に着きました。
天気がとてもよく、赤岳もくっきりきれいに見えます!
そしてこれから、酪農体験が始まります!
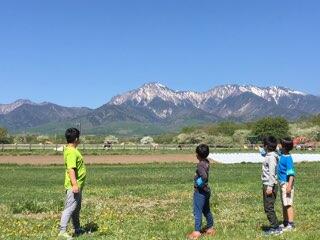
天気がとてもよく、赤岳もくっきりきれいに見えます!
そしてこれから、酪農体験が始まります!
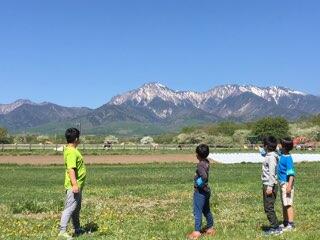
0
JR最高地点
標高1375メートル地点で JR小海線が通過するのを見ることができました。集合写真を撮って次の場所へ!


0
閉校式
飛ぶ鳥跡を濁さず という言葉を目標として、班で協力しながら片付けを行いました。そして、たくさんの感謝を大成荘の方々に伝えました。
これから、バスに乗り込み出発です!

これから、バスに乗り込み出発です!

0
朝食バイキング
朝から自分の食べたいものを選んで食べます。バランスよく選んで食べられるでしょうか?
今日一日の栄養チャージ!!

今日一日の栄養チャージ!!

0
2日目の朝
清々しい朝が始まりました。
体操をして眠気を吹き飛ばし、今日も一日ケガなく楽しく、仲良く過ごしましょう!!

体操をして眠気を吹き飛ばし、今日も一日ケガなく楽しく、仲良く過ごしましょう!!

0
キャンプファイヤー
火の神さまより、友情の火 努力の火 希望の火 が 灯りました。
キャンプファイヤーレクの始まりです。

キャンプファイヤーレクの始まりです。

0
バイキング夕食
3種類のカレーから、好きなものを選びます。そして、すきなおかずをトッピング。
ついつい食べ過ぎてしまいそうです!

ついつい食べ過ぎてしまいそうです!

0
大成荘に着きました
開校式が始まりました。
一泊二日お世話になります。気温は大体10度異なるとのこと。協力して働く共同生活の始まりです。
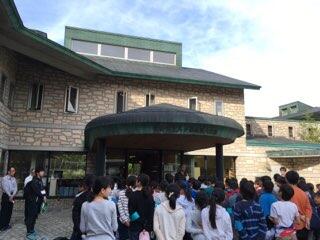
一泊二日お世話になります。気温は大体10度異なるとのこと。協力して働く共同生活の始まりです。
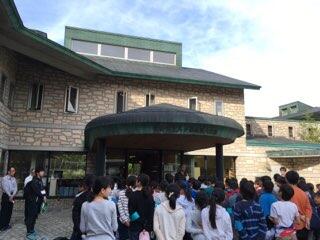
0
本日の給食
日野市GIGAスクール構想
リンクリスト
Netモラル(保護者向け)
カウンタ
2
3
1
1
5
9
3
過去認定状況
学校情報化優良校

(2016年4月から2018年3月まで)

(2016年4月から2018年3月まで)