令和6年度・7年度 東京都教育委員会体育健康教育推進校
令和6年度・7年度 日野市教育委員会研究奨励校
令和8年2月6日(金)研究発表会開催
研究主題「たくましい子供の育成 ~体育・食育・健康な生活をとおして~」
「平山小からだ健やかプロジェクト ~体育健康教育~」
「一人一人を大切にする魅力ある楽しい学校」「自分とあ・な・たを大切に」
平山小学校合唱団
第91回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール金賞受賞日本一
第92回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール銀賞受賞

文字
背景
行間
令和6年度・7年度 東京都教育委員会体育健康教育推進校
令和6年度・7年度 日野市教育委員会研究奨励校
令和8年2月6日(金)研究発表会開催
研究主題「たくましい子供の育成 ~体育・食育・健康な生活をとおして~」
「平山小からだ健やかプロジェクト ~体育健康教育~」
「一人一人を大切にする魅力ある楽しい学校」「自分とあ・な・たを大切に」
平山小学校合唱団
第91回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール金賞受賞日本一
第92回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール銀賞受賞

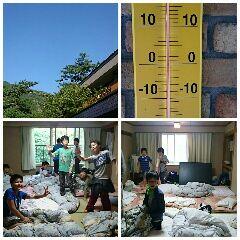


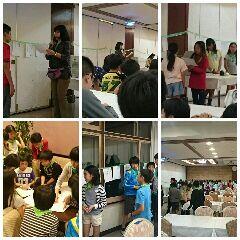
・令和5年度の日野市立平山小学校PTA規約です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
・令和6年度のPTAニュースです。