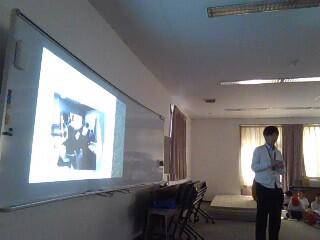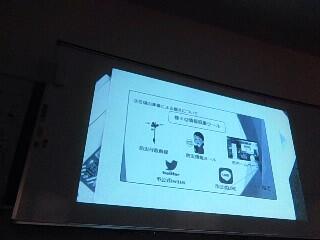文字
背景
行間
日誌
ようやく、虫捕り実施!
9/2(土)に水辺の楽校主催の虫捕り、9/15(金)に3年生が水辺の楽校の皆様の協力を得て虫捕りを行うはずでしたが、それぞれ、「酷暑」のため中止・延期に。
3度目の正直となりましたが、ようやく3年生が理科の授業で、水辺の楽校の皆様の協力をいただき、浅川の河川敷で虫捕りを行いました。

多くの子がマイ虫捕り網、マイ虫かごを持ち込んでいます。(保護者の皆様、ご協力いただき、ありがとうございます。)
やる気満々の子供たち。
最初に水辺の楽校の方の説明を聞きます。
・自分より背の高い草の中には入らないこと
・大人から見える範囲のところで探すこと
・基本的にはキャッチ&リリースになること
延期にも関わらず、再びご協力いただいた水辺の楽校、日野市緑と清流課の皆様、どうもありがとうございました。
早速、四方八方に散って、虫捕り開始!
捕まえた虫を水辺の楽校の方に見せに行く子供たち。図鑑片手に、虫の特徴などを説明してくださいます。
酷暑の影響か、全体的に大物は少なかったようですが、立派なバッタを捕まえた子も。
互いに捕獲した「獲物」を見せ合います。
30分ほどとった虫捕りの時間もあっという間に過ぎていきます。
ふれあい橋から見ると、虫捕りをしている子供たちが、まるで虫のようで・・・。思わずパチリです(笑)【校長】
秋の交通安全期間
現在、秋の全国交通安全運動期間中です(9月21日~30日)。
定期的に学区内を自転車で回り、登校する子供たちにあいさつしなから声をかけるのが校長の習慣になっていますが、今は、交通安全期間中ということもあり、いつもより、重点的にパトロールをしています。
高幡の交差点です。
日野交通安全協会の皆様の誘導に従い、信号機を見ながら安全に横断歩道を渡っています。
高幡不動駅前です。
本校のスクールガードボランティアでもある「桃太郎おじさん」に元気よくあいさつしていく子供たちです。
新井団地の入り口付近の見通しの悪い交差点です。
いつもここに立ってくださっているスクールガードボランティアの方から、横断歩道を渡らず、友達を走って追いかけていて、車にぶつかりそうになった子がいたとのお話を伺いました。
ここは、写真のように、急に奥から自動車がやってくることがあります。
写真の児童のように、横断歩道をゆっくり渡り、車の有無を確認してから細い路地に入るようにしてほしいと思います。
学校でも指導していますので、通学路でこの交差点を通るご家庭の保護者の皆様は、お子様に注意を促してくださいますようお願いいたします。【校長】
委員会発表集会
本日(9月27日)の朝、オンラインで委員会発表集会を開催しました。今年度、本校では、11の委員会が立ち上がり、5・6年生の児童が日常の当番活動やイベントの企画・運営など様々な活動を行っています。本日は、図書委員会と集会委員会が発表をしました。
<図書員会の発表の様子>
図書委員は、主に図書室の整備や読書活動の推進活動を行っています。
<集会委員会の発表の様子>
集会委員は、主に児童集会の企画や運営を行っています。
少しずつ紹介を行っていた委員会発表集会は、今回で終了です。どの委員会も、クイズを盛り込むなど、発表を聞くみんなが「笑顔」になる工夫を凝らしたスライドを作成し、発表をしてくれました。発表をしてくれた5・6年の皆さん、ありがとう!
全天候型体育館完成!
屋根がついてるんだから、最初から全天候型体育館じゃないか・・・とツッコまないでください。
ようやく、空調機設置工事が終わり、本日、検査が終了して、正式に学校に引き渡しになりました。
本日の放課後、多くの教職員が参加し、空調機の操作方法等の説明を受けました。
体育館の壁面に10台、空調機が設置されました。
それぞれに防球ガードが取り付けられています。
これで、体育等で思いっきり活動しても大丈夫です。
家庭の空調機と同様にワンタッチで操作できます。
温度の上げ下げも簡単にできます。
配電盤の説明も受けました。
便利にはなりますが、つけっ放しにしないなど、節電に気を付ける必要があると感じました。
ちょうど涼しくなったときに空調機が設置されるという皮肉な形になりましたが、これからオールシーズン快適に使える体育館になったことは、教育活動の幅を広げそうです。
冬季から早春に実施される12/2の開校記念式典、R6.2.16、17の学芸会、R6.3.25の卒業式なども快適に過ごせるようになることを期待しています。【校長】
阿川園に行ってきました!
「ねぇ、校長先生って、給食に出てくるくだもので、一番何が好きなの?」
校長「なし!」
と即座に答えるほど、梨が好きな校長。
今日の5・6時間目に3年生が、本校に梨をはじめ、果物を提供してくださっている阿川園に社会科見学に行ってきました。
梨の木が生い茂る中で見学する子供たち。
背の高い子は、頭がついてしまいそうです。
校長も頭がついてしまうので、屈みながら歩いていると、
3年生A「校長先生、おじいちゃんみたい!」
と声がかかります。
校長「杖はどこじゃ?」
3年生たち「あはは」
たわわに実る梨に、子供たちの目もくぎ付けです。
3年生B「この梨って、ネットでしか買えないの?」
校長「そんなことないよ、直売してくれるよ。」
3年生B「おいしそうだなぁ。買ってもらおうかな。」
説明していただいた阿川様から様々な梨を見せていただき、興味津々の3年生たちです。
3年生は、社会科で日野の農業について学んでいきます。
学校のそばにも、こうした田畑や果樹園などがあるので、子供たちにも関心をもってほしいと思います。【校長】
東西潤徳小学校コラボレーション~本格熊本郷土料理交流編~
構想から3か月。
今月の学校だよりでも紹介しました(学校だより9月号.pdf)今回の交流。
満を持して実施です。
最初に、今回の企画の発案者でもある本校の栄養士から、メニューや給食交流の意義について説明があります。
ここからは、校長がタブレットを持って、各学級を回り、両校に生中継します。
本校は、22学級ですので、じっくり回っていると、時間がかかってしまいますので、各学級を回りつつ、各学年で感想を言う代表児童の学級を1つ決め、そこを重点的に中継するようにしました。
こちらは、4年生の様子です。代表児童は、「生実食」をして感想を述べていました。
6年生は、特別に代表児童を3名出して、感想を伝えました。
最高学年のサービスです。
5年生、1年生、2年生、3年生の代表児童の様子です。
子供たちからは「太平燕(タイピーエン)がおいしかったです。」という感想が多かったです。
後半は、山都・潤徳小からの中継です。
本校と同様に、池部校長先生が自らタブレットを持って、各教室を回ります。
サービスで、学校の外も映してくださいました。
山都・潤徳小のグラウンド側には山があり、学校の裏手は田んぼが広がっていることが分かって、子供たちも驚いていました。黄色くなってきた稲穂がとてもきれいでした。
山都・潤徳小6年生代表「今度は、東京の給食も食べてみたいです!」
検討はしているのですが、日野を代表する料理がなかなかないので・・・難航しています。
最後に、山都・潤徳小の調理員の方に、詳しく熊本の郷土料理について教えていただきました。
山都・潤徳小調理員の方「高菜ご飯は、阿蘇地域の郷土料理です・・・太平燕は、昔はよく給食に出ていたのですが、アレルギーが厳しくなってきて、最近は少なくなってしまいました・・・がね揚げは、天草地方の郷土料理でカニに見立てたサツマイモのかき揚げです・・・。」
聞いていて、旅番組を見ているように感じます。
本場の話には引き込まれます。
今回は、全校交流ということもあり、各学級、大フィーバー。
交流を始めて10か月になりますが、本当に、両校の絆は深まったと実感します。
個人的には、「がね揚げ」がおいしかったです。3時のおやつにいつもほしいなぁ・・・。【校長】
(山都・潤徳小の給食は、こちら)
(本校の給食は、こちら)
(山都・潤徳小の交流の様子は、こちら)
水害から市民を守るために
社会科で「水害からくらしを守る」の学習を進めている4年生。
これまで、消防署の方にお話を伺ったり、山都・潤徳小の子供たちと一緒に学習を行ったりしていますが、今日は、日野市防災安全課の皆様においでいただき、水害から市民を守るためのお話を伺いました。
今回のポイントは、消防、警察、自衛隊等の組織と市が連携して災害への対応を行うことです。
市では、大きな災害が発生すると、市長をトップとした災害対策本部が立ち上がります。
ここから、様々な指示が出て、関係機関と迅速に連携できるわけです。
日頃から図上訓練などを繰り返し行っていると説明がありました。
また、災害発生時には、防災無線をはじめ、SNSを活用した情報発信を工夫しているとのことです。
さらに、災害に備えて、家庭で備蓄するすることが大事たという話がありました。
大きな災害が起きたときは、3日分の飲料水・食料の備蓄が必要とのことです。
日頃から、3日分の飲料水・食料を備蓄しておき、古いものから消費し、新しいものを継ぎ足すという習慣(ローリングストック)をつけるとよいとの紹介がありました。
最近は、充電器やモバイルバッテリーの準備も重要になってきているとのことでした。
子供たちからは、様々な意見や感想が発表されました。
市の方々が、万が一の事態に備えて、様々な準備をしてくださっていることに理解が深まったようです。
こうした学習を通して、家族ぐるみで防災意識が高まることにつながってほしいと思います。【校長】
「大福」の健康診断
本校での唯一の飼育動物、烏骨鶏の「大福」ちゃん。
今日は、年1回の健康診断の日です。
今日は、9月の委員会活動の日でもあります。
担当の獣医の先生に飼育委員会の活動場所までおいでいただき、烏骨鶏の飼育に関する基礎的な内容を教えていただきました。
烏骨鶏は、何と、キジの仲間だそうです。
若い時には、卵を年間50個ほど産むそうで、栄養価の高い良質な卵ということです。
烏骨鶏の抱き方や、健康状態の見方などを分かりやすく教えていただきました。
実際に飼育小屋に行って、「大福」の健康診断です。
最初に体重を量りました。
袋の中に入れて計測するのですが、さすがの「大福」もちょっと袋の中に入るのを嫌がります。(そりゃ、そうですよね・・・)
何とか、袋に入れて、計測したところ、体重は、1.3kgでした。
子供たちも「軽いね~」と驚いていました。
「大福」の体調を確認します。
羽の下は黒い皮膚になっていました。子供たちもびっくりです。
毛のつやもよく、健康だとのことです。
「大福」は7~8歳とのことで、人間の中年にあたる年齢だそうです。
まだまだ元気いっぱいとお墨付きをいただきました。
伸びた爪を切ります。
「大福」は、何をされるのか分かっているのか、おとなしくしています。
「かわいい!」と見つめている飼育委員たちから自然に声が漏れます。
「大福」には、個体を識別できるようにマイクロチップが埋められています。
今回の健康診断結果も登録です。
健康診断が終わると、自分から飼育小屋に戻っていく「大福」。
本当に賢くてかわいらしいです。
お忙しいところ、子供たちにご指導いただいた獣医の先生にお礼を言って健康診断は終了です。
本校のオリジナルキャラクターの「サクラモチ」のモデルでもある「大福」。
本校のアイドルとして、これからも元気に愛嬌を振りまいてほしいと思います。【校長】
秋が来た!
今朝の東京の気温は20℃を下回りました。
夜もちょっと、寝冷えを心配するような感じでした。
先週までの酷暑が何だったのかと思うくらい、一気に季節が進んだ感じがします。
秋分の日を過ぎ、ようやく秋到来です。
今日の10時頃の暑さ指数(WBGT)の数値は22.8で、「注意」レベルでした。
外での活動は、ほほ問題なくできる数値です。
2時間目、2年生は、校内の畑のところで虫探しをしていました。
残念ながら、虫はほとんどいなかったようですが、猫じゃらしなどで植物遊びを楽しんでいました。
3年生は、国語で「ちいちゃんのかげおくり」を学習しています。
休み時間になると、かげおくりを試している子たちがいます。
「ひとうつ、ふたあつ、みいっつ・・・とお!」
じっと、自分の影を見つめた後、青空に目を移します。
3年生A「あ、校長先生、かげぼうしが空に上がったよ!」
ちいちゃんの気持ちに迫れたでしょうか。
教育実習生と外で遊んでいる3年生たちもいます。
実習期間も今週で終わり。濃密な1週間にしてほしいものです。
3時間目の体育で、手つなぎ鬼をして遊ぶ1年生たちです。
キャーキャーと大きな歓声が上がります。
校庭の反対側では、4年生たちが走り高跳びに取り組んでいます。
よい記録を出せば、今からでも中国・杭州で行われているアジア大会に間に合う・・・かな?【校長】
体育館、復活!
空調機設置工事のため、6月中旬から使用禁止となっていた本校の体育館。
記録的な猛暑となり、校庭で体育ができないときは体育館を使いたかったのですが、それもできず、苦しい期間が続きました。
このたび、ようやく、工事が終了し、体育館が使用できるようになりました。
体育館に行ってみると、早速、2年生が体育をしていました。
校長「体育館、何が変わったか、分かる?」
2年生たち「あれだよ!」
子供たちの指さす先には、工事が終わったばかりの空調機があります。
体育館のフロアは使えるようになりましたが、空調機の最終検査があるので、空調機が使えるようになるのは10月以降になりそうです。
久し振りに体育館で鬼遊びです。
とても楽しそうに追いかけています。
別の2年生の学級では、授業終了時に振り返りをしていました。
担任「久し振りの体育館体育、どうでしたか?」
2年生A「いっぱい走ることができて楽しかったです。」
2年生B「体育館が使えるといいなぁと思いました。」
校長「何が変わったか分かる?」
2年生たち「クーラー!」
校長「夏は涼しい風が、冬は暖かい風が出てくるんだよ。だから、1年中、気持ちよく体育などができるようになるよ。」
2年生C「だから、冬に行事をやるように変わったんだね。」
2年生女子D「校長先生、大好き!」
校長が工事をしたわけではないのですが・・・。まぁ、愛の告白は、ありがたく受け取っておきましょう(笑)【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)